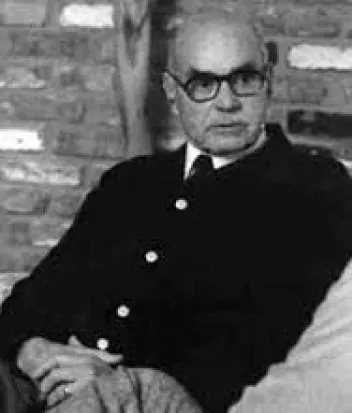α要素・β要素|ビオンの思考の生成・成熟過程
ビオンは,「思考の理論」において,人には最初から「思考」があるのではなくて,そもそもは「考える」という段階に達していない感情や感覚(β要素)というものがあり,それをどうにか思考化し,処理できるもの(α要素)にするために「考える装置」が出来上がる,その考える装置の働き(α機能)によって感情や感覚が思考になるという考えを提唱しました。ここでは,ビオンの思考の生成・成熟過程におけるβ要素,α要素に関する説明の抜粋を記述します。
ビオンの思考の生成・成熟過程におけるα要素とβ要素
ビオンは感情や情緒の感覚印象を思考化する必要があるということを理論化し,β要素,α要素として思考の生成・成熟過程をグリッドの垂直軸に表わした。
- β要素🌿:赤ん坊が認識できない,内在化できない感情や思考を原初思考。まだ処理されていない生の感覚的・情緒的経験のことを指し、これらは主体によって十分に消化されていない,表象化以前の原初的な心的内容物です。これらはまだ思考として形になっておらず,感覚的印象や未加工の情緒的経験
- α要素🌿:β要素(生の感覚的・情緒的経験)がα機能によって処理・変換された結果生じる心的内容物です。
- 意味を持ち,精神的成長や学習に貢献できる内容
- 意識的に利用可能な形に変換された心的内容
- 言語化や象徴化が可能になった経験
- 思考,夢,記憶,概念として利用できる素材
- 心の中で保持,結合,関連付けが可能な要素
- 赤ん坊の心の中で現れたり消えたりするような,赤ん坊が持ち始めた断片的な視覚像のようなものから,より洗練され精緻化された表象までの幅がある。
さらに,この思考化にはα機能をもつ対象の存在が必要であるとし,分析家が精神分析で担う役割がこのα機能なのだという話をしている。しかし,なかなかβ要素,α要素水準の思考,夢思考・夢・神話水準の思考というものがつかみづらく,あちこちから拾ってきた説明を一度書き出してみることで,なんとなく外観がつかめそうな気もして,もし誰かの役にも立つことがあれば…。
出典
後ろのカッコ書きはどこから引っ張ってきたかをメモしていたものについては書いておいたという参考程度です。
(宇宙)は松木邦裕「精神分析体験ーービオンの宇宙」,
(パ)は「 パーソナル精神分析事典」,
(体系)は「体系講義対象関係論上」,(発見)は「分析臨床での発見」,
(事典)はLopez,C. R. の「ビオン事典」,(RB)はVermoteのReading Bion,です。
年号が入っているものはBionの著作からの引用であることがはっきりしているものです。
- 1959 連結への攻撃
- 1962 考えることに関する理論
- 1962 経験から学ぶ
- 1963 精神分析の要素
- 1967 変形
- 1970 注意と解釈
- 1982/1992 熟考
- 1990 ブラジリアン・レクチャー
β要素
- 自分のうちに内在化できない原初思考
- 考えられないもの/考えることには適さない
- 考えられず,具体的に扱われるしかない原始的な思考・考え
- 処理されていない生の感覚印象,情緒印象,E
- いまだ心的なものとなっておらず,それゆえ生命を持たず飽和しており,成長する可能性がない。
- いまだ心に充当されてこなかった,そしてそのためにものとしての状態を有する,現に存在する諸思考もまたβ要素と見なされる。(RB)
- 考えられず,排出や呑み込みと具体的に扱われるだけのもの
- カントの言う,もの自体,ヌーメノン1963
- 死んでいて非現実の対象(1982/1992)
- 志向が生じると想定される際早期の母胎であり,物である思考
- 象徴化の前提となる表象を欠く,非表象領域の思考
- 夢見られなかった未消化な諸事実(事典)1959
- 貯蔵はされうるが,α要素のように記憶を表象せず,「消化されない事実」をあらわす。
- 現象とは感じられず,もの自体で,無意識になることはできず,それゆえに抑圧されることや,抑制されること,経験から学ぶために用いられることもできない。(事典)
- ただ貯蔵するか除去するかしかない
- 投影同一化で(具体物としての心から)排出されることでしか操作されない(宇宙)
- 投影同一化か行動化によってしか排泄されえない。(RB)
- 外界の具体物であって,内界に置かれる思考にならない(宇宙)
- 精神病部分が支配している心に溢れているもの
- 赤ん坊は自分が知覚するもの(飢餓感,排せつ欲求,寒さ・暑さ,身体の痛み,満足感などと概念化されるもの)を自身では考えることができず,何か分からない苦痛な具体物か,快な具体物でしかない。それらがβ要素である。母親のα要素を通してそれらは意味づけられる。α機能は母親が保持し,代行している。(パ)
- 感覚的・身体的に近い特質(α要素はより心的になった特質)(ブリトン)(ブリトンによればβがαに修正される過程を思考の算出の基礎とした)
- 生の描写,具体水準の描写,究極の事実,もの自体(本来,ある場面の生の描写は不可能な物。しかし,それを提示しないと後の提示と解説が意味をなさないために示されているもの。本来は思考ではないのだが,それがのちに生まれる過程を説明するために必要である。したがって,β要素という記述は究極の事実の不適切な変形であり,偽造である(パ)
- β要素の出現は,α機能がまだ働いていないか,機能不全にある心による。他の思考では起こり得る現実化がこの水準では起こらない,飽和されない。(宇宙)
- 思考がものと区別されず,そのため心がものを動かす筋肉であるかのように働くことになる種類の思考
- 思考が生じると想定されるその再早期の母胎であり,物である思考(1962)
- 記憶できない「消化されていない事実」(1962)
- β要素が集まって凝塊化されるとβ要素幕が形成される。この膜が意識と無意識の機能の混乱状態を引き起こす。それは精神病者に見られ,相手への排せつや破壊を目的として,情動的な掛かり合いを相手に喚起する。(1962)
- β要素はもの自体である具体物なので,互いに結合する力を欠いており,そのモザイク的な凝塊(β幕)はその結合壁に不具合な隙間を作る。
- β幕が作られると,夢が見られなくなる。意識と無意識の境界がないため。夢が現実の具体的な出来事として体験される。
- β要素が私たちの内側での現実化によって断片的な視覚像として保持されるようになると原始思考としてのα要素となる。
- ある種の非言語的なコミュニケーション,一般的には子供やパーソナリティの精神病部分あるいは精神病患者に追って使用される,おそらく直感的なコミュニケーションの一種を表す。これらの個々人は,中小物をワークスルーする(消化する,代謝する)ためのα機能を書いているので,知的に概念化されえないβ要素を用い,それゆえ,投影同一化のメカニズムによってコミュニケートする。1974a
- まったく考えられないことについて話す方法1990
- α機能が機能しない場合,情緒と同様に感覚印象は手つかずのままで,夢思考を生み出すために使えないβ要素になる。代わりにそれらは刺激の増大からの制振装置の負担を軽減させる投影同一化を通して排出されるし,同様に行動化という形状を取る。このような放出は筋肉の動きや表情などを通して行われるか,または操作に適したある種の排出的思考においても使用される。1962.1990
- こころがあたかも筋肉であるかのように作動すると感じられる心的な領域において操作されるもの(1967)
- β要素を取り扱う筋肉活動的な行為を「具体的な投影同一化」と表現した
- 「じゃがいもは歌われない」(1967)(←こころにはおかれず,考えたり思ったりはできないことをビオンがこのように言った。外部にあるもの自体としてのじゃがいもっは「成長したり,抜かれたり,食べられたり」はしても,それが歌われるためには変形されて思考として内部に置かれなければならない(宇宙)
- β要素も思考や夢を含んでいるが,心で活用されるようになるために夢作業が必要となる(RB)
- 知覚装置を通してその人物が得た感覚データ,または感覚印象は私たちの内部に置かれるものに変形されねばならず,その変形されて内部に置かれているものが思考,β要素はもの自体であって,思考ではない,こころにはおかれない(宇宙)
α要素
- 初めて内界に生成される思考(宇宙)
- 心の中にあるものではあるが,現れたり消えたりするような,
- 赤ん坊が持ち始めた断片的な視覚像と呼べそうなもの
- 過去のある一場面の,切り取った写真の一部のような視覚像(パ)
- 視覚像に似ている思考の萌芽型
- 原始的思考や感情と見なされうる1997
- 生きている現実の対象(事典)1992
- 貯蔵に適しており,夢思考の構成要素(RB)
- α要素の中でもより萌芽的(原初的)なものはほぼ非表象領域の思考
- クラインのmemory in feelingはα要素に近似する心的事象
- 考えるときに使用している思考の最も原初的な水準にあるそれ
- 萌芽的と言える水準のα要素があって,初めて人は表記や記憶,考えることと言ったフロイトの言う現実原則に基づくこころの二次過程,意識下に関わる心的機能が作動できるようになる(パ)
- 視覚聴覚臭覚パターンであり,それとして記憶されうるもの
- 多義性を有する「象徴」として機能するまでには至らないもの
- α機能により消化され,そのおかげで内的対象として思考に利用できる,記憶できる
- β要素より成熟していて考えられるものになる原始思考
- α機能が働くと,感情の感覚データはこころの中に置かれるα要素に変形され,それから認識され意識されうる思考へと進展し,空腹,眠い,悲しいなどの言葉になる。
- 意識するという操作はできないが考えられる思考
- 考えることがコンテインできる,内在化された「もの自体」とも表現できる,フロイトの表現での感覚的印象が含まれる萌芽思考(宇宙)
- α機能が感覚印象に作用した結果,(β要素のように)外的現実世界の対象ではなく,そのような現実に関連すると信じられている感覚単位に作用した内界の産物(宇宙)
- α要素の構造のひとつめは,外的出来事のインパクトを表象し,二つ目はその出来事の「消化」という内的過程である。(1992)
- ①情緒体験→夢作業α(α機能)→α要素→物語化→夢
- α機能によって取り扱われる外的情緒経験を表す。そのα機能が外的情緒経験をα要素に変換させ,物語化(歴史的順序)過程を経由するようにする。 α要素化された外的情緒経験は覚醒生活の情緒経験に近似でき,貯蔵や意識的覚醒時思考に適したものにできる。
- ②一つの展開する物語の中のように,パーソナリティが参与する覚醒時の出来事の感覚的知覚→夢作業α(α機能)→夢思考
- 第二過程の間に,貯蔵されてきた物語はパーソナリティが睡眠もしくは覚醒している時の無意識的夢思考に使われるようにするα要素へと変えられる(1962,1992)
- 心的に消化された事実(1982)(パ)
- 還元できないほどに簡素な諸対象(1982)(パ)
- 現実の,生きている,善なる諸対象(1992)(パ)
- 心的で,個人的,主観的,高度にパーソナルなもので,その人物の認識領域に特異的かつ明確に属していると想定される(1982)(パ)
- 象徴ではないが象徴や表意文字として使うようにできるもの(1982)(パ)
- 「精神病者は心的質を知覚できる。しかしそれをα要素に変形することができない」(1982)(パ)
- 「α要素なしには,何も知ることはできない」
- 「友人に話している人は,この情動経験の感覚印象をα要素へと変形しており,それによって夢思考ができ,ゆえに事実について,それが関与する出来事かその出来事への彼の感情か,あるいは両者かに関わりなく,混乱していない意識を持てるようになる」
- 思考操作することが可能な形に変えられた感覚データ(発見)
- 感覚データのままでは,人が主体性のもとに認識し,思索することができない。意識的無意識的な思考操作が可能になった感覚データがα要素(発見)
- 「私たちが夢においてよく知っている視覚像に似ている」(1962)(パ)
- 「還元不能で単純な対象である」(1962)(パ)
- 「夢思考や目覚めていながら無意識的に考えること,記憶の能力が供給を当てにしているもの」(1962)(パ)
- アイデンティティや自己の感覚をもたらす夢思考を創る素材を心ん衣供給する抽象的概念(事典)1967
- 接触障壁の透過性とα要素のおかげで,意識状態と無意識状態の揺れの中にあり,脳は決して休まない。一方が眠っている間にもう片方は覚醒したままにされる。(事典)1992
- 夢作業との区別としてα機能には一連の段階,a.感覚印象に注意を払うこと,b.その印象を記憶に貯めること,c.それらを表意文字に変換すること,d.心を支配する原則に依拠すること,が必要である。(事典)
- 「増殖するにつれて融合し,接触障壁を形成する」(1962)(パ)
- 接触障壁は半透膜的に意識と無意識をほどよく区別するので,夢が成立する。(精神病者の場合,夢は断片化されたβ要素からできているため,目に見えない視覚性の幻覚(見えないものの幻視)に類似するため,精神病者は夢を見ない。
- 夢・夢思考・神話
- α要素が連結(融合)し,象徴化を持つようになったもの
- この水準の思考は象徴としても機能する
- 行為,象徴,視覚像,物語性から成り立っている思考
- この水準では無意識と意識が区別される
- これがより成熟すると成立した無意識に前概念が置かれ,それが意識におかれると概念となる。
- α要素/感覚印象の内的相当物が連結し,連続して物語詩絵を持つことで成立する,視覚要素の大きい,具体物が象徴として働く思考(宇宙)
- 眠っている時か,無限状態の時という覚醒した意識の時とは異なる意識部分で為す思考。
- ここでの「神話」には私的な神話を含む。
- 嘘をつくことはこの水準にある思考。嘘をつくためには考える人が必要であり,言葉を重ねて作話が必要である。(1970)(宇宙)
- それらが存在するという直接の証拠がある。(RB)
- アイデンティティや自己の感覚をもたらす(事典)1992
- 覚醒時の夢思考によってα要素をさらに精緻化した結果である。(RB)
- 覚醒時の夢思考とは,進行し続ける無意識的プロセス。「考えること」は精神が連続的に感情や知覚,思考を処理する過程。(RB)
α機能
- 外部に知覚されている者,目や耳や口や皮膚という知覚器官から得られるその感覚データ(感覚印象)を私たちの内側に彫像され考えられるもの(原思考であるα要素)にするための機能。考えることというコンテイナーが持つ機能を通して,原思考から発達-成熟的に変形していく機能。
- 感覚データをα要素へと変換して,精神に夢思考のための素材を共有する。それによって覚醒したり,眠りに入ったり,意識的になったり,無意識的になったりする能力を提供する。(1962考)
- 精神科を初診する人の中に苦悩を言葉で表現できない人たちいるが,それは感じている苦痛苦悩を概念化できず,感情は内的なものに変形できないβ要素,もしくは変形されていてもα要素,または未発達の夢思考・夢・神話水準の思考である。(パ)
- α機能はいくつかの因子からなる機能と一致し,自我の機能を含み,感覚素材をα要素へと変形する。(宇宙)
- α機能は構造,つまり接触障壁を算出する心的装置と見なされるかもしれない。
- 経験から学ぶためには,α機能が情動的経験への気付きに対して作用しなければならない(1962)
- 無意識的に考えること/夢見ること,もの想いこそが,原初的思考を成熟させ,真実としての情緒体験を理解する道を拓く。これこそが経験から学ぶために必要なものである。(体系)
- 非言語的な転移現象には,β要素,α要素水準の思考が含まれている。
- α機能によって,感情や欲動、衝迫が内在化され,後に言語表象に繋げられる,言葉として意識化し考える対象にできる(体系)
- α機能の働きは知覚された感覚データ(視覚,聴覚,味覚と言った末梢近く気に知覚されたそのままの感触そのもの,生物としての感覚そのもの,生のデータ),もしくは感覚印象を原子型の思考であるα要素に変えることである。(発見)
- 感覚印象という外的な知覚痕を思考という操作可能なものに変える心的機能(パ)
- 自らの真実である情緒体験の感覚印象をα機能・無意識的に考えること/夢見ることによって「思考」に変形させ,意識的思考へと成熟させていく(体系)
夢作業α
- 夢の生成は,日中の刺激からの残渣物を使って夢思考を作り上げる。
- それに抑圧や圧縮などの加工を施して顕在夢を作る。
- 夢として報告されるものは消化不良のサイン,夢作業αの失敗(1992)(RB)
- 夢の象徴化と夢作業が記憶を可能にする(1992)(RB)
- 感覚刺激の残渣物から夢思考を作る。
- 外部から感知されたものを内部で扱えるものに変形する作業
- 無意識水準で感知された感覚印象の原初水準での思考化
- この種の変形作業は睡眠中になされるだけではなく,覚醒時にも無意識裡になされている(覚醒していて夢見ること)
- 夢作業を可能にするには,他の人々による,もしくは内在化された彼らの一側面―内在化された乳房―によるコンテインメントが必要(RB)
- β要素,α要素とβ要素の混在,イデア/観念はこの「乳房の機能」のもとへと表れて変形される。この消化が起きて初めて,これらは利用可能となって心に充当される。(=心的要素は心に充当されないままの状態にとどまることがある→豊かな夢生活を使用してもα機能が働かない場合,治療者の覚醒時の夢機能の助けがなければ,夢生活から利を得ることはない)(RB)
精神分析との関連
- アナライザンドは言葉や振る舞いによって考えや思いをその空間に排出する。分析家はそれをみずからの中に取り入れ,自身のα機能を使って,その意味を掴み,言葉による解釈で伝える。このモデルは母親のα機能にある。(宇宙)
- 精神分析において解釈をするということは,患者にはより思考の原始水準で捉えられている内的体験を,夢思考・夢・神話水準の思考や概念水準の思考と言った水準の高い思考に変形させる働きかけである。(パ)
無意識的空想との関連
・フロイトは空想と思考を分けており,クラインは無意識的空想が意識化されることでそれが考えられるようになる(それが分析作業である)とし,それを引き継いで現代クライン派は無意識的空想を意識的思考に変更すると考えているが,ビオンは,原始的思考が洗練した思考に成熟するのであって,無意識的空想の本質は思考であると主張している。つまり,無意識的空想を思考として認知している。(パ)