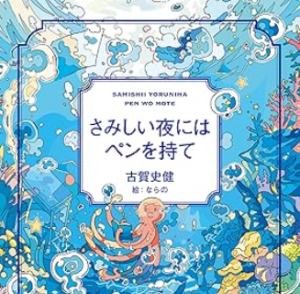人の話を聞いて,なぜこんなに疲れてしまうのか――ビオンの思考の理論と「自他の境界」から考える
人の話を聞いていただけなのに,終わったあと,ぐったりと疲れてしまった。
聞いていた自分の方が,暗い気持ちになってしまった――。そんな体験,ありませんか?
「この人と話すと,いつもなんとなく疲れるな…」と感じる相手っていませんか?
今回は,「人の話を聞くことの疲労感」について,精神分析家ビオンの「思考の理論」と「自他の境界」という視点から,少し深く考えてみましょう。
話すこと ≠ 思考すること🧠
人の話を聞いて疲れる――その「疲れ」の正体は,相手の「思考されていないもの」を受け取ってしまっているからかもしれません。
精神分析家のウィルフレッド・ビオンは,「思考すること」そのものを深く探究した人物です。
彼は,まだ意味づけされていない感情や体験を「ベータ要素」,それを内面で整理し,思考として扱えるようにする力を「アルファ機能」と呼びました。(ベータ要素とアルファ要素については「もやもやした思いを言葉にするということ」でも詳しく触れています)
つまり,言葉が発せられていても,それが「整理された思考」になっているとは限らないということ。
ときには本人ですらどう感じているのかわからないまま,「吐き出す」「投げつける」ように語られる言葉もあります。
言葉に見えても,思考されていない「ベータ要素」の例🌀
たとえば,次のような言葉は,「ベータ要素」がそのまま言葉になっている可能性があります:
- 混乱したままの不安や怒り💢
- 自分でも整理できていない過去の経験
- 相手にぶつけたいけれど説明できない感情
これらは「言葉」にはなっていても,「思考」にはなっていない。そのようなベータ要素を受け止めると,聞き手の心には,処理しきれない混乱や疲れが残るのです。
ベータ要素がもたらす「聞く側の疲れ」とは?🤯
ビオンは,母子関係をモデルに「アルファ機能」のはたらきを説明しました。
赤ちゃんが感じた混乱や不快感(=ベータ要素)を,母親が受け取り,やわらげ,赤ちゃんに返してあげる。
そうすることで赤ちゃんは,自分の体験を「思考」として処理できるようになります。
私たち大人も,日常のなかで無意識に,相手の混乱を受け取り,なんとか理解しようとする「母親役」をしていることがあります。
でも,自分にアルファ機能を働かせる余裕がないとき,その未処理のベータ要素はただただ「重たいもの」として残り,心をすり減らしてしまいます。
「ベータ要素っぽい言葉」に気づくためのヒント🔍
ベータ要素は,日常会話のなかにも紛れ込んでいます。
- テンション高く話しているのに,どこか話の芯がないとき
→ 不安を紛らわせるためだけに話しているのかもしれません - 自慢話や武勇伝を延々と聞かされるとき
→ 承認欲求や不安が整理されないまま投げ出されている場合も - 何が言いたいのかわからない相談
→ 本人の中で状況や気持ちがまとまっていない可能性があります - 明るい雑談のようで,なぜか疲れるとき
→ 未消化の感情が言葉の背後ににじみ出ているのかもしれません
疲れを強める「無意識の思い込み」⚠️
疲れの原因はベータ要素だけではありません。
「聞くこと」にまつわる無意識の思い込みも,心を消耗させていることがあります。
✅ 相手の“裏”を読まなきゃ…🕵️♀️
「この人,本当は違うことを思ってるかも」
「地雷を踏まないようにしなきゃ」
相手の裏を探ろうとし続けると,言葉の内容以上に神経を使ってしまいます。
✅ 意見は一致していなきゃいけない🧍♀️
「同じ考えじゃないといけない」
「わかってあげられない私は冷たい?」
でも,違いがあるのは自然なこと。その違いを“いけないこと”と感じてしまうと,心の自由が奪われてしまいます。
✅ 相手の機嫌は自分の責任?🧳
「この人,機嫌悪そう。何かまずいこと言ったかな…」
「空気を壊しちゃダメだ…」
相手の感情まで自分で引き受けてしまうと,それはもう「聞く」ではなく,「背負う」になってしまいます。
「聞く力」は,自分の心を守る力とセットで育てられる🛡
話を「聞く」ことは,単に耳を傾けることではありません。
未整理の思いを受け取ったり,無意識の期待を引き受けたり,不要な責任を背負いこむこともあります。
だからこそ,聞くには,自分の心の余裕と「健全な自他の境界」が必要になります。
相手の話をちゃんと受け止めるには,まず自分の心のスペースを確保することが大切です。
最後に ――「聞くのがつらい」は,自分を守るサインかもしれません
「聞くのがつらい」と感じたとき,それはあなたが未熟だからでも,優しくないからでもありません。
それは,「もう今の自分には受け止めきれない」という,心からの大切なサインです。
無理に受け取ろうとせず,いったん距離をとること。
それは「聞くことを手放す」のではなく,「自分を取り戻すためのプロセス」なのです。
疲れやすさには理由があります。それを理解することが,あなたの「聞く力」を守り,育てる第一歩になるかもしれません。
桜心理カウンセリング恵比寿では,人との関係に疲れてしまう,どうしてこんなに疲れてしまうのか,この先ずっとこんな感じなのか…という思いを抱いている方に精神分析的心理療法を提供しております。
恵比寿・広尾から徒歩で,渋谷からはバスでアクセスの良い場所です。興味のある方はお問い合わせください。
桜心理カウンセリング恵比寿HP